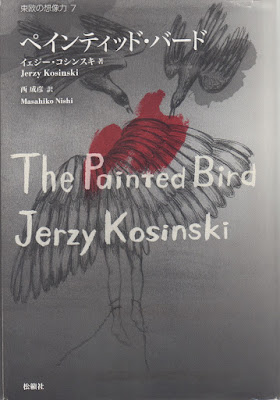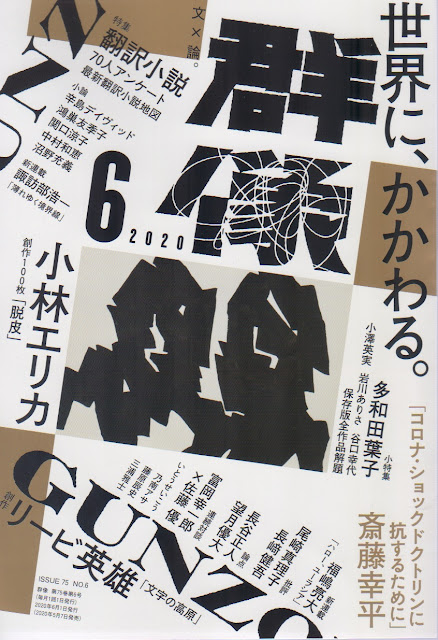福永武彦の『ゴーギャンの世界』(新潮社、全集版)とバルガス=リョサの『楽園への道』(河出文庫)から。
「そして彼は[1865年]以後の六年間を海上で暮し、水夫や火夫や舵手を経験し、成年以後は水兵となって、その間に南米やインドやスカンジナヴィアへ行った。それは恰もボードレールが、二十歳の頃モーリス島[モーリシャス島]へと旅行し、その航海の体験が、後年のボードレールの詩作を彩っているのと似てはいないだろうか。こうしてゴーギャンが二十三歳でフランスへ戻った時に、母親は既に死に、姉は嫁ぎ、彼には家庭もなく家もなかった。後見人のギュスタヴ・アローザが、彼をパリの、ラフィット街の株式仲買商ベルタンに紹介した。ここから平凡な一人の株屋の生活が始まる。」(福永、21ページ)
前便に引き続き『楽園への道』では船員時代のことは、こんな風に書かれている。
「 (前略)船員だった頃、外洋でルツィターノ号やチリ号の船倉や船室で、何度も彼はそのように振る舞った[男色の趣味についてからかわれると相手の顔を殴っていたということ]。それらの商船で三年を過ごし、その後、戦艦のジェローム=ナポレオン号で、プロイセンと戦争状態にあった時期に二年を過ごした。(中略)その頃のおまえは、世界のあらゆる海や港を、あらゆる国や民族や風景を訪ねながら、ベテランの船員として経験を積み、やがては船長になることに憧れていた。(中略)見習い水夫としての最初の航海はフランスからリオ・デ・ジャネイロまでで、三か月と二十一日かかった。」(バルガス=リョサ、91ページ)
船乗り時代に訪れた場所は、『楽園への道』では、「リオ・デ・ジャネイロ、バルパライソ、ナポリ、トリエステ、ヴェネツィア、コペンハーゲン、ベルゲン[ノルウェーの古都]」とある。
バルパライソは当然、マゼラン海峡経由だろう。チャールズ・ダーウィンがビーグル号に乗ってここを通ったのが1834年のことだ。
ゴーギャンは23歳で船を降りた後、11年間株式仲買人をやり、その合間に印象派の画家の作品を蒐集する。カリブ海出身のピサロと知り合い、絵を学び始めたのもこの時期だ。ゴッホとも知り合った(1886年)。
そしていよいよカリブ海へ行く。1887年のことである。
「一八八七年五月から十月まで、初めはパナマ、次いでマルティニック島のサン=ピエール郊外での苦難続きの滞在をとおして、おまえは本物の画家になったのだ。フィンセントがそれを最初に見抜いた。それに比べれば、蚊に刺されながらレセップス氏の運河の工事現場でつるはしを手に日雇い労働者として働き、マルティニックでは赤痢とマラリアで死にそうになったが、それくらいのひどい目はどうってことはないだろう。そのとおりだった。カリブのまばゆい太陽に照らされたあのサン=ピエールの絵の中では、色彩が熟した果物のように炸裂し、赤、青、黄、緑、黒などの色彩が主導権争いをするかのように剣闘士の獰猛さで互いに競い合ってい」(バルガス=リョサ、98-99ページ)た。
パナマに行った経緯は福永の本に詳しい。
「この姉[ゴーギャンの姉マリイのこと]は、良人であるジュアン・ウリーブが、当時パナマのコロンにいて商売を営み、弟をそこへ差向けようと考えた。(中略)明るい南国への誘惑は、その間にも彼の心の中に燃え続けていた。」(福永、38ページ)
ゴーギャンの姉の夫がパナマでやっている商売はやはり運河がらみなのだろうか。
「無一文の彼はとにかくパリを逃げ出し、野蛮人として太陽の下で暮したかったのだ。パナマは彼の魂の故郷であるペルーからは近い。彼の中の血が自然の華かな色彩、強い香気、青い海を呼んでいたに違いない。」(福永、39ページ)
彼は妻への書簡には以下のように書いている(1887年4月)。
「……画家としてのこの私の名前は一日ごとに有名になって来ている。が、今のところ、私は三日位は何一つ食わないことがよくあるのだ。こいつは健康をそこなうだけでなく、私の気力までもそこなってしまう。この気力という奴を私は取り返したい。私がパナマへ行くのは野蛮人[傍点あり]として生きるためだ。私はパナマ海峡から一海里のところに、太平洋の中の小さな島(タボガ)を知っている。そこは殆ど住む人もなく、自由で、豊穣なのだ。私は自分の絵具と筆とを持って行き、人間共から離れて自分を鍛え直すつもりだ。」(福永、38ページ)
太平洋の小さな島を知っている、というこの書き方もずいぶん思わせぶりだ。どうして知っていたのだろう。この島はパナマ市から20キロ南の太平洋に浮かぶ小島だ。
大航海時代、パナマ越えをして太平洋に至り(太平洋の発見)、その後ペルーを征服するフランシスコ・ピサロとヌニェス・デ・バルボアがこの島を踏んでいる。
このカリブへの旅に付き添ったのは弟子のシャルル・ラヴァル。彼らはこの島に3ヶ月滞在したが、絵筆は握らなかった。だからパナマ時代の絵は一枚も残っていない。しかしこの島にはゴーギャンが立ち寄ったことを示すプレートがビーチに据え付けられている。
運河工事の人夫として働いて病気になったのでタボガ島へ行ったという話もあるが、この書簡からすればそもそもの目的がこの島に行くことだったわけだ。この手紙の書きっぷりにはすでに、その後タヒチでのゴーギャンが見える。
しかし義兄は職を用意してくれなかった。パナマでは結局この時期進んでいた運河の工事の人夫となって「朝の五時半から夕の六時まで炎天の下で働き、ラ・マルチニックへ行く旅費をためようとした。」(福永、39ページ)。
ということは最初の目的はパナマ(タボガ)で、思そしてマルチニークに行った、つまりハプニングだったのだ。
そしてゴーギャンとラヴァルは6月にマルチニークに到着。
「小さな首都サン・ピエルから反時間ほどの土人の小舎に住んだ。(中略)それは全くの楽園だった。黒人の男や女はひねもす歌い、空は晴れ、大気は暑くしかも風は涼しかった。(中略)そこは確に、彼の感覚を悦ばせる風景に富んでいたが、しかしラ・マルチニックは後のタヒチのように、個性ある作品を生み出させるまでには至らなかった。(中略)この楽園での生活はものの半年とは続かなかった。二人は飢えていたし、虚弱なラヴァルがまずマラリアに罹った。ゴーギャンもそれに感染し、更に赤痢に罹った。彼は殆ど死にかけて骸骨のように痩せ衰え」、「十一月に、弟子をサン・ピエルの病院に入れると、水夫として帆船に乗り込んで、単身パリへ戻って来た。」(福永、40ページ)
バルガス=リョサは、福永が書いていないゴーギャンの性に並々ならぬ関心を寄せて描く。
「サン=ピエールでのうだるような夜、燃えるようなクレオール語を話す、腰のほっそりした黒人女の一人を組み伏すことができたとき、女ヴァイキングに再会したら、遅ればせながら教えてやろうと。(中略)マルティニックでの作品は熱帯の桁外れの色彩のおかげで描かれたのではなく、絵を描くことと同時にセックスすること、本能を大切にすること、自分の内にある自然なものと悪魔を受け入れ、自然のままに生きる人間として欲求を満たすことを学んだ画家、未開人としての新参者が勝ち取った、因習からの自由と精神の自由のおかげだった。(中略)あの不運続きのパナマとマルティニックの旅から戻ったとき、おまえは野蛮人だっただろうか。そうなりはじめていたところだったね、ポール。いずれにしても、もうおまえの振る舞いは文明化されたブルジョワのものではなかった。パナマの密林の中、情け容赦なく照り付ける太陽の下でシャベルを振るって汗を流し、混血女や黒人女を、カリブの泥や赤土や汚れた砂の上で愛したあとで、どうしてそんなふうに振る舞えようか。」(バルガス=リョサ、101ページ)
-------------------------
下は秋晴れの日の東京。