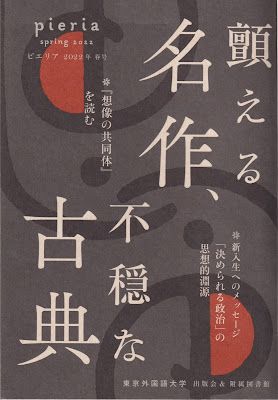11月に入って、窓から見える木々も一気に紅葉が進んで、この1週間であっという間に緑が消えつつある。でも銀杏はまだ黄色になっていないので、そこはもう少し踏みとどまってほしいところだ。このまま銀杏並木が秋景色になってしまうと、そこはもうすでに冬の一歩手前だし、そこからは駆け足だ。
ペドロ・アルモドバルの映画『パラレル・マザーズ』を見た。この映画はこれまでのアルモドバルと違う。
1 一回見ただけで、ストーリーがすべてわかる。
アルモドバルの映画は入り組んでいて、どんな映画だったのかを説明しようとすると、意外にできないことが多い。『バッド・エデュケーション』とか『抱擁のかけら』とか、見直さないとストーリーが思い出せない。鑑賞者の理解を超えた展開やスピードがあるからなのだと思うが、『パラレル・マザーズ』は一見しただけでたちどころに説明が可能である。
2 初めてスペイン内戦に取り組んだと言われている。
歴史記憶法は制定されたものの、予算措置がなされないために遺骨発掘作業が進んでいないと聞いていたが、確かにこの映画でもそのような背景が説明されている。そしてストーリーの大枠として遺骨発掘の困難からその成果までが語られている。母親の一人であるジャニスが、若い母親のアナに「歴史がわからないと自分たちの居場所がわからない」(正確なセリフではないが大体こういう内容)を説く、というよりお説教する(しかしこの場面、え?・・・と思わずにはいられなかった)。
3 DNA鑑定が使われる。
産院での乳児取り違えを軸に人間ドラマが展開するので、DNA鑑定が出てこないわけにはいかない。Aは100%の確率でBの生物学的母親ではない。Cは99,99999999999%の確率でBの生物学的母親である。
2の内戦と関わってくるが、この「科学的手法」は、暴力的に殺害された家族の遺骨発掘作業で生きてくる。だから、ストーリー上必要なのでしょうけれど、うーん・・・まあそういうものなんでしょうけれど。DNA鑑定の絶対的信頼性に寄りかかって作られていること、つまり映画の外に絶対的な物差しがあるというのでいいのかな、と。
4 アルトゥーロが浮いている。
登場人物の一人で法人類学者のアルトゥーロは最初は妻ががんでジャニスとは一緒になれる状況ではないということだったが、その後妻の病気が治ったために自分も自由になった・・・と進む。この人だけは、まるで往年のアルモドバル映画のような、いい意味での出来過ぎの設定がされる。一人だけフィクション世界を生きている。
5 映画の最後にエドゥアルド・ガレアーノの(たぶん)名文句が引用される。
この部分、引用が長い割にあっという間に過ぎてしまって、なんだったのか理解不能。引用するならもっと長く映してほしい。
DNAで言えば、『フリエッタ』では生物学的な母娘の別離があり、映画のクライマックスは、そんな二人の再会の可能性が示される。この結末は原作のアリス・マンローの短編とは真逆で、それはそれで面白いと思った。『パラレル・・・』はその延長でもあるのかもしれない。
この週末もまたかなりのメールを書いた。