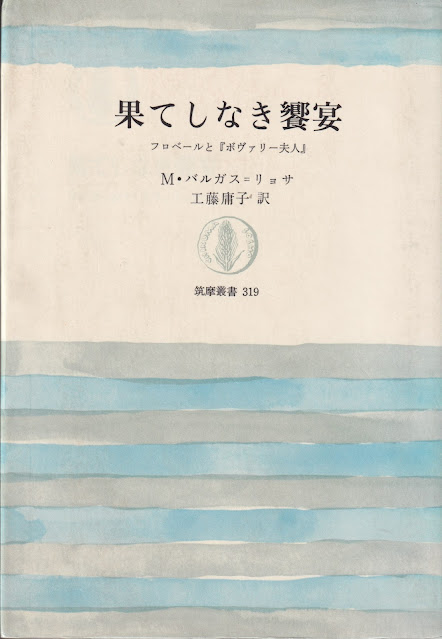4月21日、総合文化研究所で、大江健三郎追悼企画が催された。部屋は若い人から年配の人でぎっしり埋まり、しばらく体験したことのない、いい緊張感と柔らかさに満ちていた。
その前の4月15日のことも書きたいのだが、それは次の機会に。
--------------
バルガス=リョサの『緑の家』で用いられている自由間接話法を考えるさいには、バルガス=リョサがフローベール『ボヴァリー夫人』を論じた『果てしなき饗宴--フロベールと『ボヴァリー夫人』を参考にする必要がある。
『ボヴァリー夫人』のことでは、芳川泰久氏(新潮文庫の翻訳者)が自由間接話法について書いている。彼は翻訳のさい、「できるかぎり原文を忠実に」「フローベールが打った文のピリオドの位置を変えない」で、つまり「句点を同じ位置に打つ、原文を勝手に切ったり、つなげたりしない」ようにしている。(カギカッコ内は新潮文庫版の芳川氏の解説から引用。以下も同じ)
彼によれば、これまでの翻訳はそうしたことをせずに文を切ってしまっている(原文にはない句点を打っている)。そうせざるを得なかったのは、話法の切り替わりが原因である。しかしその話法の切り替え--「間接話法の地の文で、カンマやセミコロンひとつで、それが自由間接話法に切り替わる」--がフローベールが挑んだ革命的な方法なので、むしろ翻訳はそれを伝えなければならないというわけである。
芳川氏の解説から自由間接話法の訳し方についてさらに引いておくと、「間接話法ではあっても、直接話法の言葉づかいを真似て訳そうと決め」「過去形の時制に縛られず(中略)一人称にはしない(中略)、かといって三人称のままにもし」ない。そして日本語には「そんな中間的な便利な言葉」があり、それを「使用した訳文」があるとのことだ。面白い。ちなみにその「便利な言葉」が何かは読むとすぐにわかる。さてなんでしょう?
芳川氏の訳文と話法に関する解説の箇所を読み、さらにバルガス=リョサがやはり注目している話法のところを『果てしなき饗宴』で確認してみた。
「いわゆる自由間接話法(中略)は、ある曖昧さをふくんだ叙述形式であることを、まず確認しておこう。語り手が登場人物にきわめて近いところで発言するために、読者はときおり、話しているのは登場人物にほかならないという印象を受ける(中略)。自由間接話法の本質は、この曖昧性、もはや語り手のものではないが、登場人物のものでもないらしい視点の混同、あるいは不確実性にある。」(『果てしなき饗宴』工藤庸子訳、p.234-235)
芳川氏の言うように、一人称でもなければ、三人称でもないように訳すべきと考える視点の曖昧さである。
原文で読んでいないので気づかなかったが、芳川氏の翻訳にある「傍点」は原文ではイタリックになっている箇所だ。バルガス=リョサは「イタリックは語り手の交替と視点の瞬間的な変化を意味している」と書き、イタリックにしたのは、自由間接話法を最初に実践したフローベールがその「試みの大胆さに気遅れし、混乱を避けようとしたのだろう」と言っている。
「物語はおかげで【自由間接話法のおかげで】軽快になるとともに凝縮され、同時に(中略)各部分(文章やパラグラフ)において、小説の総体が到達すべき全体性が、再現されることになる。ほんの短いテクストのなかで、同時に二つの観点から、つまり不偏不党の観察者と筋書に参加する登場人物の両方の観点から、ひとつの出来事が語られるのだ。」(p.236)