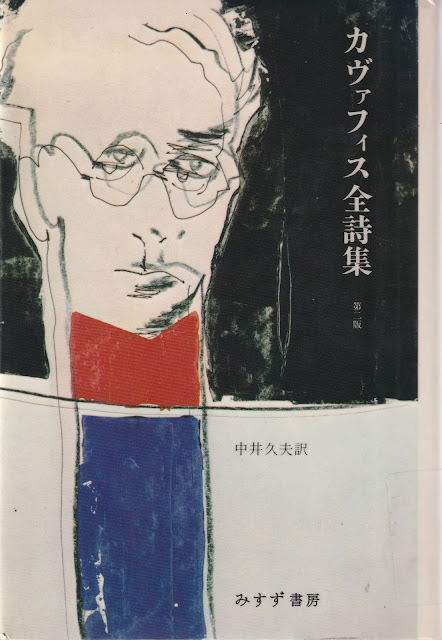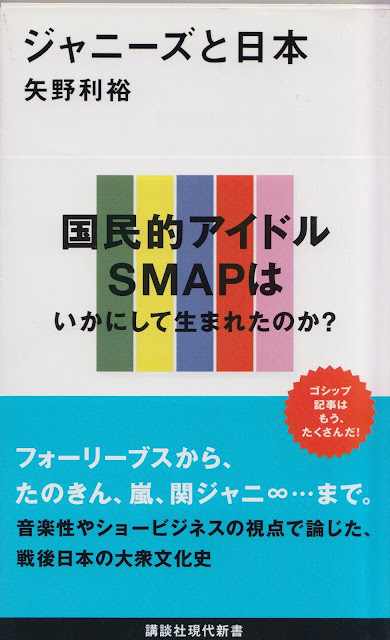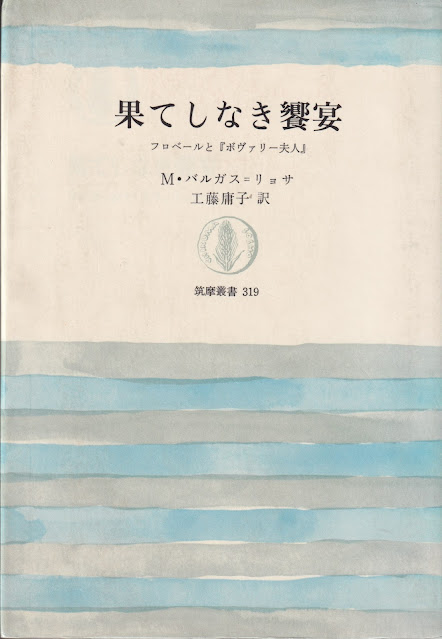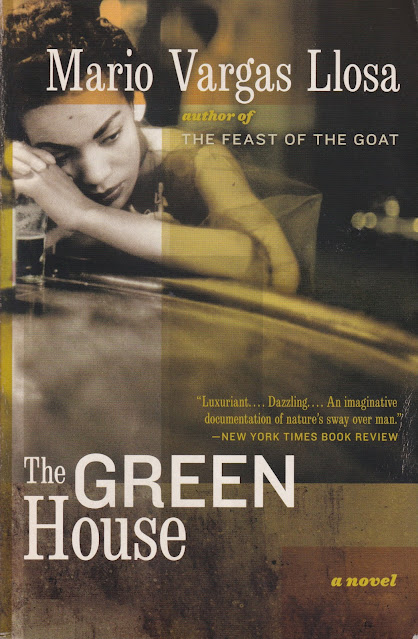フアン・ガブリエル・バスケスの『密告者』(服部綾乃、石川隆介訳、作品社)には、第二次世界大戦中のコロンビアに移住したドイツ人移民の中にいたナチ信奉者、あるいはそう目された者たちが出てくる。
カリブ沿岸の都市バランキーリャにはナチ党の支部があったと書かれている。これは史実と一致する。バランキーリャにおけるナチに関して多くの記事があるが、しかしそれらが報じられたのは、このバスケスの小説が出て以降のように思われる。少なくともこの小説が出るまで、というよりこの小説が日本語で翻訳されるまで知らなかった。
バスケスのこの小説はおそらく多くのコロンビア人にとっても貴重な内容なのだが、一見難しい語りの手法をとっている。
第4部でコロンビアにおける有力な人物(ガブリエル・サントーロ)が実は、あるドイツ人をナチ信奉者だと「密告した張本人」であったことが暴露されるシーンが出てくる。
そこはテレビ番組におけるインタビューの再現形式になっている。インタビュアーは番組進行役で、その人のセリフはイタリックになっていて、答えるのはアンヘリーナである。アンヘリーナが暴露する側である。
-----------------
【原文】
¿Estaba ella al tanto de la reputación de Gabriel Santoro?
No. Bueno, cuando Angelina lo conoció, Gabriel estaba metido en una cama como un niño, y eso no realza la apariencia de nadie, hasta el presidente se vería disminuido y común reducido al piyama y las cobijas. Angelina sabía, (後略)
【英訳】
Was she aware of Gabriel Santoro's reputation?
No. Well, when Angelina met him, Gabriel was tucked up in bed like a baby, and that doesn't enhance anybody's appearance, even the President would look diminished and common reduced to pyjamas and bedclothes. Angelina knew, (後略)
【久野による仮訳】
ガブリエル・サントーロの評判について彼女は知っていましたか?
いいえ。実はアンへリーナが彼と知り合った時、ガブリエルはベッドに赤ちゃんのように入っていて、そうなっているとどんな人もぱっとせず、大統領だってパジャマと毛布だけの小さな普通の人に見えてしまうものです。アンへリーナは知っていました、(後略)
------------------
ここは三人称に対する問いかけになっている(彼女は知っていましたか?)。これをそのまま読めば、インタビュアーは、インタビュー相手とは別人の「彼女」がガブリエル・サントーロを知っていたかどうかを聞いていることになる。
それに対しての答えも、そのまま読めば、質問されている人とは別人の「彼女」のことについて答えている。その別の人とはアンへリーナで、アンへリーナがガブリエル・サントーロと知り合った経緯を話している。
スペイン語文法の人称を正確に反映させて読もうとすれば読もうとするほど、ここは三人称に引っ張られる。スペイン語の授業などでこの小説のこの部分を取り上げればそう読む人は出てきておかしくない。
しかしここでインタビューされているのはアンへリーナであり、アンへリーナが自分のこととして答えている場面なのだ。このインタビューの再現は以下のように書かれている方が理解しやすい。
¿Estaba usted al tanto de la reputación de Gabriel Santoro?(あなたはガブリエル・サントーロの評判を知っていましたか?)
No. Bueno, cuando lo conocí, Gabriel estaba metido en una cama como un niño, y eso no realza la apariencia de nadie, hasta el presidente se vería disminuido y común reducido al piyama y las cobijas. Yo sabía, (後略)(いいえ、実は私が知り合った時、ガブリエルは……)【下線部が変更箇所】
こう書かれていればインタビューで交わされた会話のそのままの再現なのだとわかる。
スペイン語でこの本を読む人たち(あるいは欧米言語一般の読者:いわゆる標準ヨーロッパ言語[SAE]のこと)は三人称が用いられても、不思議な印象はないのだろうか?それともここの場面に見られるバスケスの手法は実験的になるのだろうか。
あらためてこの場面を整理すると、この物語の語り手である一人称の「yo(英語のI)」がこのインタビューをテレビで直に見て、その内容が重大であるために書き起こしている。つまり重要なのは、インタビューを見ている人「による」再現になっていることだ。
画面の中にインタビュアーとインタビューされるアンへリーナがいて、インタビューが始まる。これを語り手の「私」から見た語りとして地の文にするとどうなるか。
Yo vi en la televisión que el entrevistador le preguntaba a Angelina que ella había estado al tanto de la reputación de Gabriel Santoro. Vi que ella decía que no, bueno, cuando Angelina lo conoció...(私はテレビで、インタビュアーがアンへリーナに、ガブリエル・サントーロの評判を知っていたかを尋ねるのを見た。私は見た、彼女がいいえ、実は知り合った時……と言うのを見た。)
おそらくこうなるのではないか。スペイン語の時制は想像なので間違っているかもしれない。ただ、欧米言語で物語る場合には、このようにして語り手というのが絶対的に存在し、その枠は揺るがない。したがって語り手が私という一人称であれば、その人物が他人の行為について見聞きしたものは、基本的に従属節的になる。場合によっては主節を省いて従属節の部分だけをそのまま書き込んでいく。つまり自由間接話法である。
この時に欧米言語では人称は間接話法のものがそのまま残る。会話を再現しているのは「私」であって、「私が見たもの」が大きな枠として設定され、その目線から再現される以上、テレビの画面の中での出来事は三人称で語られる。「私」はインタビュアーにも、アンへリーナにもなれない。
非欧米言語話者、日本語話者(日本語は主題優勢言語。SAEは主語優勢言語や主語卓越言語と言われる)として読むと、人称が不自然に見えるが、欧米言語の語りの規範からすれば三人称であって当然なのだと考えられる。あくまで「私」が、インタビュアー(彼)のアンへリーナ(彼女)に対する質問とその答えを再構成しているからである。
ところでSAEを主語卓越言語とする言語類型論についてだが、小説を読む上でSAEは「人称卓越言語」と言ったほうがわかりやすいかもしれない。卓越性があるのが主語か主題かというよりも、問題は人称ではないだろうか。主語は人称に依存しているので。
邦訳は工夫がなされていて、インタビューの再現形式であることがわかるようになっている。 ここは訳者を相当に悩ませたところに違いない。
角田光代の『八日目の蝉』は基本的に一人称で書かれている小説だが、冒頭部分に、三人称(希和子)で書かれているパートが置かれている。以下、引用。
---------
玄関に突っ立ったまま、台所の奥、ぴたりと閉まった襖に希和子は目を向けた。色あせ、隅の黄ばんだ襖を凝視する。
何をしようってわけじゃない。ただ、見つめるだけだ。あの人の赤ん坊を見るだけ。これで終わり。すべて終わりにする。明日には、いや、今日の午後にでも、新しい家具を買って仕事を探すんだ。今までのことはすっかり忘れて、新しい人生をはじめるんだ。希和子は何度も自分に言い聞かせ、靴を脱いだ。(中公文庫、7-8ページ)
--------
「何をしようってわけじゃない」から「新しい人生をはじめるんだ」までは希和子の内面の声(独白)であることは無理なくわかる。三人称の地の文に、その人の声が一人称で入ってきても、日本語では主語を示さなくてもわかるし、原文でその部分はカギカッコで括られていない。しかしスペイン語版では以下のようになる。
----------
Paralizada en el espacio que queda junto a la puerta donde se dejan los zapato, [Kiwako]dirige la mirada al fusuma de detrás de la cocina, cerrado a cal y canto. Está descolorado, con las esquinas amarillentas.
《No voy a hacer nada malo. Sólo quiero verlo aun momento. Sólo me gustaría ver a su bebé; eso es todo. Después pondré punto y final. Mañana... No, esta misma tarde compraré muebles nuevos, buscaré un trabajo. Lo olvidaré todo y empezaré una nueva vida.》Kiwako se lo repite a sí misma varias veces.(La cigarra del octavo día, Galaxia Gutenberg, p.7)
----------
希和子の独白は一人称で、しかもカギカッコ(二重ギュメ)で括られている。カギカッコがなくてもわかりそうなものだが、地の文が三人称である以上、そこにいきなり一人称が使われたら、一人称で語られた小説ととられてしまうだろう。希和子(三人称)から語るのが地の文の規範だ。