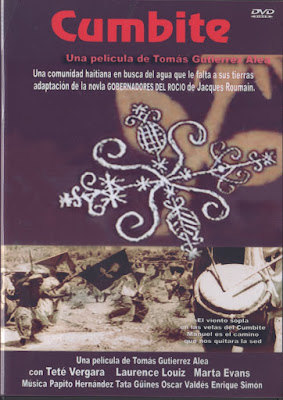1941年、レヴィ=ストロースは「ポール・ルメルル大尉号」に乗ってマルセイユを出て、マルチニークへ向かった。アンドレ・ブルトン、エメ=セゼール、ウィフレド・ラムらも乗っていた船である。
「徒刑囚」のように350人が詰め込まれ、不衛生に大西洋を一ヶ月を航海してようやくフォール・ド・フランスに入港。
『悲しき熱帯』でレヴィ=ストロースが当時を振り返る文章を読むと、その2年前、ヴィトルド・ゴンブローヴィッチがフロブリ号でグディーニャを出てブエノスアイレスに向かった時のことを『トランス=アトランティック』で書いているのとは随分違う。
「1939年8月21日、小生は、フロブリ号の船客として、ブエノスアイレスに入港するところ。グディーニャからブエノスアイレスまでの航海はすこぶる快適……上陸するのがもったいないほどだった。なにせ、二十日間にわたり、空と海のはざまで、記憶に値する何もなく、ひがな潮風に身をあずけ、波飛沫にさらされ、風に吹きさらされる日々だった。」(西成彦訳)
『悲しき熱帯』は紀行文、『トランス=アトランティック』は小説だ。だからといって、前者を真実らしさに満ちたもの、後者を虚構と見なすのはどちらも早計だろう。そんな簡単に読んではならないと思う。
レヴィ=ストロースは船中でアンドレ・ブルトンと知り合う。
「彼(ブルトン)と私とのあいだに、手紙の遣り取りによって、その後も続いた友情が始まろうとしていた。手紙の遣り取りは、この果てしない旅のあいだかなり長く続いたが、その中で私たちは、審美的に見た美しさというものと絶対的な独創性との関係を論じた。」(川田順造訳)
ますます紀行文が信じられなくなりかけるし、小説(虚構)のほうは、どこか読者を異世界に連れ込もうとしているようだ。
それはともかく、レヴィ=ストロースはマルチニークのあとニューヨークに向かうのだが、その間にプエルト・リコが挟まっている。
「こうして私は、純白に塗装したスウェーデンのと或るバナナ船で、プエルト・リコに向かった。」
この後、彼はブラジルでの調査資料(カード、日誌、ノート、地図、写真など)が原因でしばしプエルト・リコに足止めされることになる。
「入国管理当局は、私を格式ばったスペイン式のホテルに、船会社の費用持ちではあったが、監禁しておくことに決めた(中略)。そのホテルで私は、牛肉の煮込みやひよこ豆の食事をあてがわれ」た。
この食事からして、なるほどスペイン料理だなあと思ってしまう。ただそこはプエルト・リコである。
「このようにして、プエルト・リコで、私はアメリカ合衆国と接触したことになる。初めて私は、生ぬるいワニスとウィンター・グリーン(中略)の匂いをかいだ。この二つは、いわば嗅覚で感知しうる両極で、これらのあいだにアメリカ式快適さの様々な段階ーー自動車からラジオや菓子や煉歯磨きを経てトイレットに至るまでーーが並んでいるのである。(中略)大アンティール諸島というかなり特殊な背景においてではあったが、アメリカの町に共通して見られる或る様相をまず私が認めたのも、プエルト・リコにおいてであった。どこへ行っても、建物が軽快で、効果だの通行人の関心を惹くことばかりねらっている点で、いつまでも催されている万国博覧会か何かに似ていた。ただここでは、人々はむしろ博覧会のスペイン会場にいるような気がするのである。」
プエルト・リコにアメリカ合衆国をみて、さらにそこで箱庭のように保存されているスペインをみる。植民地状態が継続している。
「旅の偶然は、しばしば、事物のこのような二面性を見せてくれるものである。(中略)その後かなり経ってからのことであるが、私が初めてイギリス式の大学を訪れたのは、東部ベンガルのダッカにあるネオ・ゴティック様式の並ぶ構内においてであったため、今でも私には、オクスフォード大学は、泥と黴と植物の氾濫を制御するのに成功したインドのように見えるのである。」
ここでレヴィ=ストロースが言っている感覚は植民地の文化をやっているものにはお馴染みのものだろう。
植民地の方が宗主国の様式をより過剰に演出してみせる。マドリードの大学のキャンパスに足を入れると、なるほどここはハバナ大学だなと。
写真は2012年2月のプエルト・リコ(サン・フアン)。
-----------------
2021年度の授業が始まった。この4月、感染者の数は増えつつある中で、オンラインの授業もあるし、対面の授業もある。