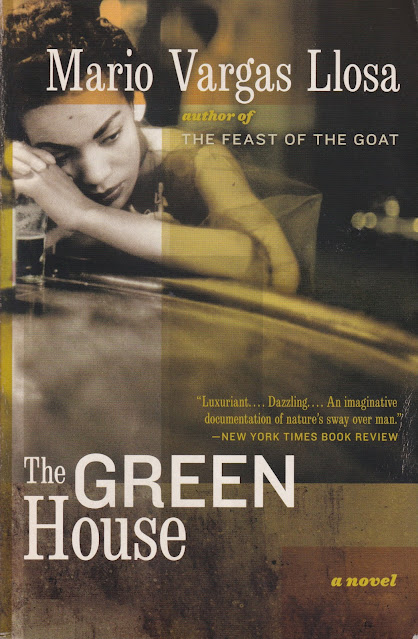El mundo cambia constantemente.
ラテンアメリカ文学、キューバの文学、カリブの文学などについてメモのようなものを書いています。忘れないように書いているというのもあるけれど、忘れてもいいように書いている。書くことは悪魔祓いみたいなもので、書くとあっさり忘れられる。それがいい。
Escribir es un acto de exorcismo. Escribir cura, alivia.
2023年3月18日土曜日
3月18日 『緑の家』と『フィツカラルド』
2023年3月14日火曜日
3月14日 バルガス=リョサ『緑の家』
【『緑の家』について最初に書いたエントリーを書き換えたもの】
この小説はまず、全体が4部とエピローグで構成されている。要するに5部に分かれている。ここにすでにこの本の読み方が示されていると考えられる。『緑の家』と題された一つの小説に、5つの小説が入っているということである。いや、5つとはいえないのかもしれない。4つの小説とエピローグと理解するべきか。
いま日本語で「部」と書いたが、スペイン語では「Primera parte(1部)」とは書かれてなく、ただ単に、Uno, Dos, Tres, Cuatro, Epílogoと書いてあるだけだ。「Libro uno(第1の書)、「Libro dos(第2の書)」と理解できる。
その5部は、それぞれが基本的に4つの「Capítulo(章)」に分かれている。1章はCapítulo I、2章はCapítulo IIと、章番号にはローマ数字を使っている。
こうして、5(部)と4(章)という二つの数字が出てくる。そしてこの「部」を見ると、Kindle版の1部は以下のようになっている。
Uno
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Uno(1部)と書かれたページをめくると文章が始まり、そこは章番号が置かれていない。便宜上その部分を0章として、しばらく進むとその部分が終わり、1章がはじまる。
つまりこの0章にあたる部分は目次には見えない、隠された部分である。小説家がこういう隠された部分を置いたら、なんらかの意味づけがあるとみて間違いないだろう。
どういうことか。1部には、トータルで5つの塊があるのだが、可視的には4章ということだ。逆から言えば、4章しかないが、実際には5つの塊がある。
本全体に言えることがここでも繰り返されている。
つまり、5つに見えもするし、4つにも見える。章の頭にある0章というのは厳密には章ではない。0+4章、つまりプロローグ+4つの章である。本全体が4つの小説+エピローグであることと対応しているのだ。
次いで章を見ていくが、一つの章は、5つのフラグメントに分かれている。ここも5が出てくる。しかも4つのフラグメントになる章もある。また5と4である。フラグメントと言っているが、これもまた便宜的な言い方である。章の中では、フラグメントが変わるごとに1行空いている。1行の空白があり、人物・舞台が違ってくるので、フラグメントの見分けがつかない人はいない。
次いで章を構成する5つのフラグメントについての説明が必要だ。便宜的にアルファベットを使う(La casa verdeのスペイン語版ウィキペディアはこの方式を使っている)。
A 伝道所(ペルーの奥地サンタ・マリア・デ・ニエバ)
B フシーア(マラニョン川を航行中)
C 兵舎(ニエバよりさらに奥にあるボルハの駐屯地)
D アンセルモ(ピウラ)
E リトゥーマ(ピウラのマンガチェリーア地区)
以上は、1部1章にある5つのフラグメントをわかりやすく説明したものだ。Aの伝道所はサンタ・マリア・デ・ニエバにあるスペイン人修道女がいる場所だ。Bのフシーアは日系人で彼は川を移動中。Cはボルハにある駐屯地の兵舎で展開する。Dはピウラに「緑の家」という娼館を建てたアンセルモに焦点を当てている。Eは同じピウラでもマンガチェリーア地区にリトゥーマが帰還したエピソード。
5つの物語ではあるが、例えばピウラが2つのフラグメントで使われている。5つに見せて4つでもある。ここも『緑の家』全体が4部+エピローグであることと同じように見える。
別の見方をすると、AとCは内容として繋がっている。そうとればやはり5つに見えて4つである。
この本は5なのか、あるいは4+アルファなのか、ということを意識して読む必要がある。
2023年3月13日月曜日
3月13日 La casa verde (7)
3部0章はもしかすると最もわかりにくいところかもしれない。
ここでは二つの時間が並行して流れている。どちらもサンタ・マリア・デ・ニエバだが、一つはカピローナの木の下の場面。カピローナというかなり高い木はアマゾンの熱帯雨林の大木。薪としても使われる。このカピローナ木周囲で展開するのをAとする。
もう一つは、シプリアーノ中尉の後にやってきた新任の中尉が軍曹らに案内された直後、フムがやってきて彼の身に起きていることを知らされる場面。こちらをBとする。時間的にはAがまずあって、それから相当の時間が過ぎてからBになる。
Aの場面ではアグアルナのフムがウラクーサから連行され、懲罰のために広場にあるカピローナの木に吊るされている。木の下にはニエバの行政官レアテギ、アレバロ・ベンサス、マヌエル・アギラ、デルガード伍長らがいる。フムはデルガード伍長が案内人ニエベス、使用人とウラクーサに立ち寄った時、彼らに襲いかかり、伍長はなんとか逃げ出し、その後、レアテギが腹を立ててウラクーサに行き、フムを虐待するとともに彼とアグアルナ族の少女とを連行した。この少女はボニファシアと思われるが、この点についてはまた別にする。いずれにしろこのAでは、木の上にいるフムが先住民語で話し、それを通訳がカタコトのスペイン語で白人たちに伝えている。白人たちが先住民に対してやりたいほうだいであることがよくわかる。これは2部3章Dの続きということになる。
一方Bだが、ニエバに連れてこられて上で書かれているように虐待され髪も切られた(髪を切られることはアグアルナにとって屈辱的なことである。髪が短いままではウラクーサには戻れない)フムはかなりの時間をこの土地で過ごしているようだ。すでにレアテギは行政官ではなく、ファビオ・クエスタに変わっている。その時間の流れは全く感じさせずにBの物語が展開するので困ったものなのだが、いずれにしても新任の中尉がやってきたので、事情を説明しようとする。そして彼が説明するのが、ウラクーサで虐待のほかもっと大切なこととしてデルガド伍長にゴムを奪われたということである。自分たちの商売を台無しにされたということだ。このパートには書いてないが、アグアルナは協同組合を組織中で、そのことがレアテギ、またとりわけペドロ・エスカビーノを怒らせていたわけだ。フムは中尉と話をするために軍曹(これはリトゥーマ)を介して面会を申し出たのだった。フムはスペイン語ができないので通訳が必要なのだが、この時通訳をやるのがニエベスである。ニエベスがここに出てくるのは意外な感じがする。
というわけで、要するにバルガス=リョサ特有の手法である二つの物語の並行なのだが、ここではその切れ目が極めてわかりにくく、同じ文章の中で場面が切り替わる。
Bueno, y que ahora le dieran algo de comer y se fuera sin que nadie más le pusiera un dedo encima, capitán, por favor que se lo repitiera él mismo. Y el capitán con mucho gusto, don Julio, llama al cabo: ¿entendido? Se había acabado el escarmiento, ni un dedo encima, y Julio Reátegui: lo importante era que volviera a Urakusa. Nunca más pegando a soldados, nunca engañando patrón, que si los urakusas se portan bien los cristianos se portan bien, que si los urakusas se portan mal los cristianos mal: que le tradujera eso, y el sargento lanza una carcajada que alegra todo su rostro redondo: ¿qué le había dicho, mi teniente? (p.249、下線部引用者)
引用では、Aから始まって、下線が引かれているところからBに切り替わる。
アグアルナに襲われて逃げ出したニエベスがフムの通訳をつとめ、フムの話の中には逃げ出したニエベスそのものが言及されるのだが、彼は素知らぬ顔をしている。またニエバに連行された少女を返して欲しいともフムは訴えるが、その少女(これがボニファシアだとすれば)とその後関係を持っている軍曹(リトゥーマ)も、そんな少女がどこに行ったのかわからないとフムに言っている。
2023年3月11日土曜日
3月11日 La casa verde (6)と近況
2部0章続き。
状況としては、前のエントリーで書いたようにイキートスからやってきたドン・フリオ(レアテギ)が、行政官のドン・ファビオ(クエスタ)と共に伝道所へ行き、修道院長とマザー・グリセルダと面会する。フリオは4年前に知り合ったボニファシアともう一人の少女をイキートスに連れて帰ろうとするが、ボニファシアが態度を硬化させたので断念する。
フリオ・レアテギはまるで少女を家政婦として働かせるために連れて帰ろうというので、マザーたちが難色を示す。
Él lo sabía de sobra, madre, por eso él y su señora siempre colaboraron con la misión, si había algún inconveniente no pasaba nada, madre, no se dijo nada, por favor que no se preocupara. La superiora no se preocupaba por ellos, don Julio, sabía que la señora Reátegui era muy piadosa y que la niña estaría en buenas manos. El doctor Portillo era el mejor abogado de Iquitos, madre, ex diputado, si no se tratara de una familia decente, conocida, ¿se habría atrevido Julio Reátegui a hacer esa gestión? Pero le repetía que no pensara más en eso, madre, y la superiora sonríe de nuevo: ¿se había enfadado con ella? (p.146-147)
「わかっていますよマザー、ですから彼も妻もいつも伝道所とは協力しているのです、なにか不都合があっても大丈夫ですマザー、おおやけになることはありません、どうか心配なさらずに。修道院長はなにも心配していませんよドン・フリオ、レアテギ夫人が慈悲深い方で、少女が信頼できる人の手に委ねられることはわかっています。ポルティーリョ先生はイキートスで一番の弁護士ですマザー、元議員です、もし家柄の良い有名な家系の出でなかったら、フリオ・レアテギはその手順を踏もうとしたでしょうか?しかし彼は、繰り返しますがその点についてはもう考えないでくださいマザー、すると修道院長は再び微笑む--彼は彼女に腹を立てているのかしら?」
フランス語訳では下線部は次のようになっている。スペイン語と同じといえば同じ。
Me Portillo était le meilleur avocat d'Iquitos, ancien député, s'il ne s'agissait pas d'une bonne famille connue, Julio Reátegui se serait-il permis de faire cette démarche?(La Maison verte, Éditions Gallimard, 1969, p.114)
この下線部について、スペイン語では主語は省略できるが、madre(マザー)という呼びかけ語があるので、se habría atrevidoだけでもフリオ・レアテギが主語であることは判断可能だろう。しかしこのようにフルネームで表記されていると、地の文のようにも読める。そして地の文だとすると、フリオ・レアテギの内面の声のようにも読めてくる。自由間接話法特有の、地の文でもあり声でもある二重性があらわれている箇所だ。しかし日本語は、地の文と実際の声では決定的に異なる。「フリオ・レアテギはその手順を踏もうとしたでしょうか?」なら発話。しかし主語がフルネームで違和感を感じるだろう。「フリオ・レアテギはその手順を踏もうとしただろうか?」なら地の文。
2部1章Aは、再びチカイスにいるel sargento(軍曹がピウラ出身であることがわかるのがここ)、el Pesado、el Chiquito、el Rubio、案内人Adrián Nieves。
このパートは自由間接話法はなさそうにはじまって、やはり出てくるがわかりやすい。伝道所から逃げ出した先住民少女たちを探している。男たちだけの下品な会話の後、眠りにつく。軍曹だけが眠らず、案内人ニエベスと話。最後の部分は次の通り。
—En cambio, usted es una buena persona, sargento —dijo Nieves—. Hace tiempo que estoy por decírselo. El único que me trata con educación.
—Porque lo estimo mucho, don Adrián —dijo el sargento—. Siempre le he dicho que me gustaría ser su amigo. Pero usted no se junta con nadie, es un solitario.
—Ahora será mi amigo —sonrió Nieves—. Un día de éstos vendrá a comer a mi casa y le pre- sentaré a Lalita. Y a esa que hizo escapar a las niñas.
—¿Cómo? ¿La Bonifacia esa vive con ustedes? —dijo el sargento—. Yo creía que se había ido del pueblo.
—No tenía donde ir y la hemos recogido —dijo Nieves—. Pero no lo cuente, no quiere que sepan dónde está, porque es medio monja todavía, se muere de miedo de los hombres.(La casa verde, p.160)