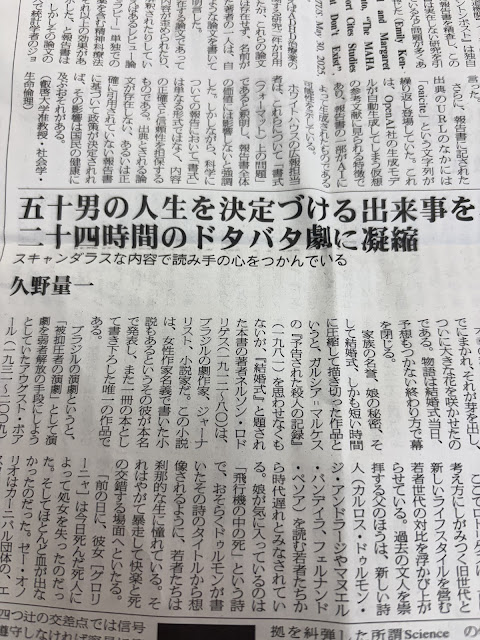El mundo cambia constantemente.
ラテンアメリカ文学、キューバの文学、カリブの文学などについてメモのようなものを書いています。忘れないように書いているというのもあるけれど、忘れてもいいように書いている。書くことは悪魔祓いみたいなもので、書くとあっさり忘れられる。それがいい。
Escribir es un acto de exorcismo. Escribir cura, alivia.
2025年12月29日月曜日
12月29日
2025年12月28日日曜日
12月28日
京橋のアーティゾン美術館で山城知佳子と志賀理江子、そして安井曾太郎やコレクションを見てきた。マキシム・パスカル指揮の読響。爽快で快速の第九は、東京芸術劇場のバージョンでは合唱団とソリストは第4楽章の途中、つまり曲の途中で入場したが、早速テレビで放送されたサントリーホールのバージョンでは、合唱団は第一楽章から入場していた。
2025年12月26日金曜日
12月26日
2025年12月19日金曜日
12月19日
2025年12月15日月曜日
12月15日
まずはホームベーカリーでパン作りから。人数は二人分。
強力粉 200グラム
薄力粉 60グラム
塩 5グラム
ぬるま湯170ミリリットル(40度くらいでいいらしいが、結構熱いのを使った)
2025年12月13日土曜日
2025年12月8日月曜日
2025年12月6日土曜日
12月6日
2025年11月21日金曜日
11月21日
2025年11月16日日曜日
11月16日
グアダルーペ・ネッテルの翻訳がでた。『一人娘』で翻訳は宇野和美さん(現代書館)。ネッテルはこれで3冊目。
考えてみれば、この世代、つまり「ボゴタ39」の世代はここ10年くらいのラテンアメリカ文学の日本語翻訳の主役を担ってきている。「ボゴタ39」とは、2007年に39歳以下だった作家たち39名のことで、短篇集『ボゴタ39』がある。
ダニエル・アラルコン、ジュノー・ディアス、エドゥアルド・ハルフォン、グアダルーペ・ネッテル、エナ・ルシーア・ポルテラ、ピラール・キンタナ、カルラ・スアレス、フアン・ガブリエル・バスケス、ホルヘ・ボルピ、アレハンドロ・サンブラが日本語で読める。10人。
いっそのこと39人全員を翻訳してしまいませんか?
2025年11月4日火曜日
11月4日
新しく映画化された『蜘蛛女のキス』を見てきた。ミュージカル好きの友人が教えてくれたのだ。この映画はミュージカルで、1992年のブロードウェイやウェストエンドのミュージカル舞台版を下敷きにしている。もちろん全ての始まりにマヌエル・プイグの同名の小説がある。その原作に基づいて制作された映画はこれまで1985年のエクトル・バベンコ監督作品しかなかったわけだが、ここに新しく、ミュージカル版に基づいて制作されたビル・コンドン監督作品のこのミュージカル映画が誕生した。『蜘蛛女のキス』のミュージカル版は日本語でも上演されたことがあるが、見たことがない。舞台を見たことがある人は映画をどう見たのか。舞台版ミュージカルの台本を見ることしかできないが、今回の映画はその台本と基本的には同じと思われる。だから英語の映画になる。今回の映画を見た人々の中でおそらく議論の的になるのは、二人の関係をどこまで描くことが許されるのか、という点だろう。プイグには「秘すれば花」とでもいうような美学があって、日本語的な文脈ではそれがプイグ人気につながった。いわゆる「ラテンアメリカ文学」との差異化がはかられていたところ(セクシャル・マイノリティを1976年に書いている)はいつでもプイグを別格の作家たらしめていたはずだ。ところがビル・コンドンは二人の関係にかなり踏み込んだ。ここは意見の分かれるところではないか。プイグは映画監督になりたかった夢をこの小説を書くことで果たした。そしてバベンコ映画では制作にかなり口出しをして、実際の監督業に近いことまでやり遂げた。プイグが生きていたのはここまでだ。彼の死後、ミュージカルではプイグの分身が劇中劇の主演を演じるまでに至った。ついにそれが映画になって、プイグは死後の生では映画の主演も演じた。原作・翻案・監督・主演。プイグは全部やってのけた。
2025年10月29日水曜日
10月29日
もうひとつはマルタ・ルイサ・エルナンデス・カデナスの「私はユニコーンではない」。チューリッヒでの映像は事前に見させてもらったが、その時の舞台よりもリラックスしていた。舞台と映像の両方からなる作品なので、スクリーンのサイズ(と映し出される字幕の文字のサイズ)が気になっていたけれども、見やすいものだった。最後のスポークンワードは、映像作家であるジョアンナ・モンテロがその場でスペイン語の表現を英語に翻訳して入力し、(おそらくAIで?)日本語に翻訳され、英語と日本語の字幕が投影されていた。
2025年10月25日土曜日
2025年10月20日月曜日
10月20日
「週刊読書人」に立林良一さんが『激動の時代』の書評を書いてくださった。2025年10月17日発売号で、ここには引用できないけれど、バルガス=リョサ研究者ならではの視点が素晴らしく、作者がこの作品を描いた背景について述べる箇所で筆が冴えわたっている。「図書新聞」で江戸さんはバルガス=リョサの『プリンストン大学で文学/政治を語る』(河出書房新社)から引用しているが、この本を訳したのが立林さんである。二人の書評はこうしてつながっている。
2025年10月18日土曜日
10月18日
「図書新聞」(3708号、2025年10月25日)で江戸智美さんが、バルガス=リョサ『激動の時代(作品社)の書評を書いてくださった。冒頭は公開されていて、電子版のバックナンバーで1号単位で読めるので、ここには引用しないけれど、あまりに素晴らしい。全部素晴らしくて感動してしまうが、とくに最後の、この小説の最終パートをめぐって書いているところに、『激動の時代』がいま読まれるべき書であることを指摘した決定的な文章がある。おそらく2500字くらいの短い文章でここまで持っていける力に圧倒される。感謝してもしきれない。いま「図書新聞」は苦境にあり、来年春の終刊が予告されているが、こういうすごい書評が載る書評紙がなくなったらどうなってしまうのだろう。これまで自分はこういう書評を書いてきただろうか。
2025年10月17日金曜日
10月17日
バルガス=リョサの『激動の時代』の書評が相次いで掲載されました。「週刊読書人」(2025年10月17日号)には立林良一さん、「図書新聞」(2025年10月25日、3708号)には江戸智美さんが書いてくださいました。ありがとうございます。
2025年10月15日水曜日
10月15日
2025年10月10日金曜日
10月10日
2025年10月7日火曜日
10月7日
2025年10月6日月曜日
2025年10月2日木曜日
2025年9月29日月曜日
9月29日
2025年9月27日土曜日
9月27日
竹橋の東京国立近代美術館で、「記録をひらく 記憶をつむぐ」を見てきた。戦争画の展示ということで図録もなければチラシも作らず、それがむしろ関心を惹いているようにも思ったが、そんなに混んではいなかった。内容重視の慎重に作られた企画で、見応えがあって、できればもう一度見にいきたい。全体がどれくらいの規模なのかがわからなかったこともあるし、こちらの頭脳の限界もあって、絵画を中心に見たために、合間に置かれた雑誌その他の資料までを丁寧に見ることはできなかった。合わせて「コレクションに見る日韓」と「所蔵作品展」も見るつもりだったので、あまりの分量で関心もあちこちに飛んでしまって、よくあることとはいえ、整理がつかないままに見たものも多かった。もったいないことをした。この前行った長崎県立美術館の展示もかなり大胆な内容だったし(ゴヤの戦争ものって結構重い)、戦後80年がこういう展覧会を可能にしたことが時期として遅かったのか早かったのか、もちろん人それぞれの受け止め方次第で、世代的なものや日頃の興味の方向に依存するとはいえ、忘れられない展覧会ではあると思うし、できれば関心を共有できる場所があるといいし、こういう展示が将来のための下地なりなんなり、踏みとどまるためのなんなりにならないものだろうか。「なんなり」ってなんなの?というのはあるけれど。
2025年9月25日木曜日
9月25日
2025年9月23日火曜日
9月23日
2025年9月17日水曜日
2025年9月15日月曜日
9月15日
世界文学・語圏横断ネットワークの21回研究会(9月13日、オンライン)でバルガス=リョサの『激動の時代』をめぐって座談会を開催しました。
アメリカ文学の都甲幸治さん、仏語圏カリブ文学の福島亮さん、比較文学の西成彦さんがそれぞれ興味深い話をしてくださり、バルガス=リョサは奥が深くて面白い作家だということに多くの人が納得した会になりました。
2025年9月9日火曜日
9月9日
2025年9月6日土曜日
9月6日
映画『遠い山なみの光』(石川慶監督)を制作するにあたって、制作者には二つの引き受けるべき、また乗り越えるべき課題があった。一つは英語で書かれたカズオ・イシグロの原作小説A Pale View of Hills(1982)と比較されることを前提にしなければならないこと。もう一つは、原作では読者の想像や解釈に委ねられた「行間」それ自体を映像として映すことをためらっていては映画にならないことだ。
「行間」ということでは、これはイシグロの長篇デビュー作であるから、その後の傑作『日の名残り』というわけにはいかない。なんとなく不完全というか、不首尾に終わっているように思えなくないところもある。訳者の小野寺健はこのデビュー作について「欲張り」なところがあると指摘している。とはいえ『日の名残り』にしても、イシグロがまだ35歳の時の長篇なので恐れ入りました、ではあるのだけれど。
それにしても、戦後80年と重ねて制作されたこの映画がなかったとしたら、この小説自体、長崎や原爆の記憶の継承が問題化された物語として読まれただろうか。そう読まれるまでに40年以上の歳月を必要としたのかもしれないし、イシグロがこの小説を書いたときには、「長崎や原爆」に近づくために、あえてそこから遠く離れる書き方を選んだようにも思える。その「遠く離れる書き方」が、40年以上が経った今の時代には適切な「遠さ」になったのだ。その「遠い」という距離感が逆にこの映画が撮られてしかるべきという根拠にもなって映画を支え、原作もまた今日的なものにもしている。非常に不思議な感覚だ。小説という個人的な作業が40年前にすでに察知し、描き出していたことを、集団的な作業である映画がようやく追いついたということなのだろうか。イギリスのシーンは古く(1980年代のグリーナムコモン女性平和キャンプの話)、それよりも前の戦後の長崎のシーンの方が新しく見えるという時間の矛盾、時代錯誤的な感覚がこの映画でもっとも印象深い。
映画では稲佐とか城山という地名と並び、若い教員が投獄された場所としてはっきり西坂と言及される。西坂とは1597年に26人のカトリック信者が処刑された地名でもあり、そこには二十六聖人記念館が建てられている。1955年には平和祈念像、1962年にはこの記念館が建立された。つまり1950年代の長崎では、原爆からの復興とキリシタン史の見直しが合流しているのだ。
21世紀に入ってからは九州を中心に製鉄や造船、石炭産業などの遺構を世界遺産へ、という動きの中で、戦艦武蔵を建造した長崎造船所の朝鮮人強制労働の実態が可視化された。高島炭鉱の三菱への払い下げにはグラバーが関わっているが、この近代化と植民化プロセスについては原作も映画も触れていない。そんなことをしたら映画も「欲張り」になってうまくいかなかっただろう。でも原作には「三菱」への言及がある。このあたりが絶妙だ。やはり小説という個人の感覚がそのまま反映できる芸術は、ここまでを含みこむ余地を持てるのだ。
悦子の友人佐知子がアメリカ兵に恋をして渡米の夢をみるのは、日本人による欧米(とその価値観)への憧れとして感情移入しやすい「美談」ということか。
イシグロにとっての40年と同じくらいの重みが、イシグロとは逆方向の移動をした労働者(インテリではなく)にとってもあったはずだが、それはどの芸術にみつけられるのだろう。
2025年8月29日金曜日
2025年8月28日木曜日
8月28日
映画『マルティネス』でチリ人のマルティネスは、メキシコの地方都市に移住して、そこで仕事を得て、数十年が過ぎて定年を迎える。家族が出てこないラテンアメリカ映画で、まるで日本映画のような、というのが第一印象。
メキシコのチリ人。これはどういうことかというと、何につけても緩いメキシコ人VS 生真面目が過ぎるほどのチリ人ということで、とりわけそれは仕事に対する考え方とか、時間感覚とかにあらわれていて、寡黙に仕事に打ち込む「世捨て人」VS いい加減な若者という『Perfect Days』を思い出したりもした。
ストーリーの鍵はチリ人の隣人が孤独死するところにあるのだが、発見までの時間が数日間とかではなく、半年間も放置されていたということで、多分この部分は実話だろう。
2025年8月27日水曜日
8月27日
2025年8月15日金曜日
8月15日
ウォルター・サレス監督の『アイム・スティル・ヒア』(2024)は冷戦期の反共軍事独裁による人権侵害を扱った実話もので、軍政とはいえ若者はドラッグを愉しみ、車を乗り回してドライブにでかけ、BGMはブラジル音楽やブリットロック、コダックの8㎜ビデオをどこにでも持っていき、流行りの映画はアントニオーニの『欲望』(1967)で、家族揃ってアイスクリーム・パーラーに出かけるようなブラジル人富裕層の暮らしは享楽的にも見えるくらいなのが普通、このまえ翻訳が出たネルソン・ロドリゲス『結婚式』(1966、旦敬介訳、国書刊行会)の雰囲気と似て、あれもリオデジャネイロだったが、ドライブ、ビデオカメラ、家族の絆という共通項がある、それでもこの『アイム・スティル・ヒア』は2024年の映画で、監督自身がこの映画で扱われる強制失踪者の家族と知り合いらしいが、左翼弾圧ということでは、このまえやっていた映画『ボサノヴァ 撃たれたピアニスト』(2023)やバルガス=リョサの『激動の時代』(2019)も冷戦期ラテンアメリカの記憶を描き、サレスは1956年生まれ、フェルナンド・トルエバは1955年生まれで同世代、バルガス=リョサは1936年生まれで少し年齢は上だが、3人が21世紀という現在地にこだわりながら制作していることは一つの共通する特徴と言えるのではないか。
2025年8月13日水曜日
8月13日
柴崎友香は『帰れない探偵』(講談社)の刊行記念選書として「場所の記憶を探偵する」というテーマで12人の作家を選んでいる。ポール・オースターのニューヨーク三部作『ガラスの街』『幽霊たち』『鍵のかかった部屋』(いずれも柴田元幸訳、新潮文庫)、W・G・ゼーバルト『移民たち』『アウステルリッツ』(いずれも鈴木仁子訳、白水社)、パク・ソルメ『影犬は約束の時間を破らない』(斎藤真理子訳、河出書房新社)、夏目漱石『彼岸過迄』(新潮社)、ジーナ・アポストル『反乱者』(藤井光訳、白水社)、テジュ・コール『オープン・シティ』(小磯洋光訳、新潮クレスト・ブックス)、東辻賢治郎『地図とその分身たち』(講談社)、レベッカ・ソルニット『迷うことについて』(東辻賢治郎訳、左右社)、奥泉光『「吾輩は猫である」殺人事件』(河出文庫)、フアン・ガブリエル・バスケス『歌、燃えあがる炎のために』(久野量一訳、水声社)、呉明益『自転車泥棒』(天野健太郎訳、文春文庫)、イーフー・トゥアン『空間の経験』(山本浩訳、ちくま学芸文庫)。選書一覧のリーフレットには、12人の作家・作品について一人ひとり丁寧に紹介文が載っていて、バスケスの部分を一部だけ引用すると、「コロンビアの作家で、私と同じ一九七三年生まれです。(中略)この数年、小説は語り直すものであることに意味がある、ある人の話をほかの誰かが語る伝聞が小説ではないかと考えています」と言っている。
2025年8月12日火曜日
8月12日 フアン・ガブリエル・バスケスと原爆
彼は平和祈念式典での長崎市長(自身が被曝2世)のスピーチを読み、核兵器廃絶の願いはかつてよりいっそう重要だと考えた。長崎市長の言葉は以下のようにスペイン語で報じられた。
“Esta crisis existencial que atraviesa la humanidad es un riesgo inminente para cada uno de quienes habitamos la Tierra”(「そんな人類存亡の危機が、地球で暮らす私たち一人ひとりに、差し迫っているのです」)。
“círculo vicioso de confrontación y fragmentación”(対立と分断の悪循環)
バスケスの心を打ったのはしかし長崎市長の以下の言葉である。
“A los hibakusha no les queda mucho tiempo”(被爆者に残された時間は多くありません)
「被爆者とは、世界中の人が知っているように、1945年の爆撃の生存者のことである。この単語は文字通り「爆撃された人」を意味する。彼らに残された時間は多くないとはどういうことか?それは要するに、原爆投下の数えきれない恐怖を身をもって経験した人々が少なくなっていき、彼らが全員亡くなったとき、出来事の生きた証言(テスティモニオ)が消えていくことを意味する。何十年も前から自らに課してきた任務、世界に証言を伝えること、経験していない人には想像のできないその経験を共有する任務にはピリオドが打たれ、私たちは資料に頼るほかなくなるということだ。
このことは当然避けられない。人間の命は有限だからだ。(中略)人々は死に、そして私たちの過去に対する理解もまた死ぬ、あるいは薄まる。それを被爆者は知っていて、だからこそ、残された時間が多くないのを知っているからこそ、懸念にとらわれているのだ。最後の被爆者がこの世を去った時に残るのは資料だけで、資料は生きた証言ではない。私たちはもちろん資料に頼らねばならないし、資料はなくてはならぬものであるし、それらが存在することに感謝するだろう。しかし直に経験した人々がこの世を去る時、私たちの間での過去の現前について、何かが失われるのだ。」
この後、バスケスは東京を15年ほど前に訪れたときに被爆者と会ったエピソードを語る。自身がジョン・ハーシーの『ヒロシマ』(法政大学出版局)のスペイン語翻訳者であることを被爆者に伝えたとき、その方が涙を流して感謝の言葉を口にした。
「いま、ハーシーのルポを読み直し、その残酷なイメージ、貴重な歴史、当事者たちの抵抗に心を動かされている。そして思うのだ。ここには、決して消え去ってはならない記憶が生きている。」
ハーシーの『ヒロシマ』は谷本牧師の「その後」で閉じられる。「その後」とは、1984年に被爆者に実施されたアンケート結果のことで、被爆者のうち54パーセント以上の人が、核兵器が再び使われると考えている。バスケスは自分がスペイン語に訳した本の最後の文を引いている。「彼(谷本氏)の記憶も、世界の記憶と同じように、まだらになってきた」。スペイン語でこの「まだらになる」はse estaba volviendo selectiva(selectivaは選択的な、の意)。
2025年8月11日月曜日
8月11日 ガルシア=マルケスの「家」
ガルシア=マルケスが『百年の孤独』を書いた家はメキシコシティのCalle Lomaにある。彼がその後、亡くなるまで住んでいたペドレガルのCalle Fuegoよりも北西に位置する。ペドレガルの家はかなり大きいが、このCalle Lomaにある家は、やや小ぶりだがメキシコシティ郊外に多く見られるような、庭があって、中は素晴らしいはずだが外側から多くを知ることができず(呼び鈴を押すと多分家のお手伝いの方が出てくる)、近くに幹線道路が走っているが少し引っ込んでいて静かで、でもちょっと勾配がある地区だが、白さが際立つことではペドレガルの家と似ている(ペドレガルの家は中に入らないと白さがわからないが)。この家をめぐってガルシア=マルケスの二人の息子が当時を回想するドキュメンタリーが製作された。題して「La casa(家)」。このタイトルは、ガルシア=マルケスが書き残した「家」という作品を意識したもので、この断章には彼が『百年の孤独』なるものを書こうとしていた痕跡が見つけられる。以下の写真は2022年の年末に撮影したCalle Lomaの家で、そのときはなんの目印もない空き家だったが、今後ここも記念館的なものに変わっていく予定だ。亡くなって10年以上が過ぎ、日々過去の人になりつつあるが、どうしてもまだそんな気分にはなれないな。ぼくにとっては優しく接してくれた気の良いおじさんで、まだメキシコに行くと、彼に言われたとおり電話しないといけないなと思ってしまって、それができないのでペドレガルの家に行こうとは思わない。最後にペドレガルに行ったとき、帰り際に家の前で写真を撮ろうとしたが、地区一帯の警備を担当している人にやめておいたら、と言われ(仄めかされて)、確かにそうだと思って撮らなかった。しかし不思議なもので、そのことで逆に、通りを渡った側から見た家の光景を忘れてはならないのだ、と強く自分に言い聞かせたのか、まだ脳裏に焼きついている(ような気がする)。
2025年8月9日土曜日
8月9日
2025年8月4日月曜日
8月4日
マリア・ホセ・フェラーダ María José Ferrada(1977-)はチリ出身の作家で、すでに何冊か児童書が翻訳されている。今回の来日で5度目だという彼女の日本滞在記にDiario de Japón(2022)があり、そこでは「ドイツは私の祖父の頭の中では、7歳まで話していた母語の響きで、その年、学校に行き、まずまずの発音のスペイン語を学んだ。チリ南部の極小の村でのことだった。祖父の両親は子どもの時、19世紀末にキールを出た船でチリに着いた。陸にあがると、着いたばかりの人は、パンのことをダス・ブロート、ビスケットのことをディー・プレッツヒェンと言い続けた」と書いている。来日中の彼女が登壇するイベントが8月15日にある。それを知ったのは、ガブリエラ・ミストラルがノーベル文学賞を受賞して80年が過ぎて、そのことを祝す催しがあったから。
2025年7月30日水曜日
2025年7月29日火曜日
7月29日
ポール・オースターがポール・ベンジャミン名義で書いた推理小説『スクイズ・プレー』では、私立探偵のマックスが契約して車を停めている駐車場係にルイス・ラミレスがいて、彼は「出版されていることがわかっているあらゆる野球雑誌を読」み、3人の息子には「それぞれ異なるヒスパニック系の野球選手に因んだ名がつけられている」。そのうえ、マックスが9歳の息子リッチーを連れて駐車場に行ったとき、リッチーはそれまで恐竜に、昆虫に、そしてギリシャ神話に夢中だったが、今度は「ルイス・ラミレスと野球の話になった。ルイスはリッチーを詰所に招き入れると、野球に関する本と雑誌をリッチーに見せた。それはまさに深遠な数字と、曖昧な人格と、難解な戦略の神秘的な宇宙への招待のようなものだった。リッチーはそれでいっぺんに野球にはまった。ルイスはかくしてリッチーのウェルギリウスになった。この神々と半神半人と人の世界におけるガイドに。それ以降、私との外出はもはや駐車場でのルイスとの会議なしには完全なものではなくなった。リッチーは私が誕生日に買ってやった〈ベースボール・エンサイクロペディア〉の三分の二を暗記しており、どこへ行くにも野球カードのコレクションを持ち歩くようになった」(ポール・ベンジャミン『スクイズ・プレー』田口俊樹訳、新潮文庫、88ページ、111ページ)。
2025年7月24日木曜日
7月24日
2025年7月23日水曜日
7月23日
2025年7月21日月曜日
7月20日
昨日神宮のナイターに行った。8対7でスワローズが勝った。勝利投手はペドロ・アビラ。登場曲はジュニオル・ゴンサレス「幸せに生きる権利がある Tengo derecho a ser feliz」。真夏の夜に流れるスタンダード・サルサ。
2025年7月19日土曜日
7月19日
4月1日から7月31日までの学内会議・打ち合わせの回数は100前後。月平均で15から20だと思っていたけれども(たぶん前にも書いたはず)、それより多くて25近い。年間では270くらいになるのかな。
2025年7月18日金曜日
7月18日 バルガス=リョサ『激動の時代』訳者あとがき 全文公開
2025年7月16日水曜日
7月16日
2025年7月15日火曜日
7月15日
藤本一勇は書いている。「現在、研究者の世界でも、翻訳の仕事は、業績ポイント上での評価が低い。外国の書物を翻訳するには、外国語ができるばかりでなく、その国の歴史や文化にも精通している必要があり、また専門書の翻訳ともなれば、原書を理解しうる最先端の知識が必要になる。(中略)/このように知的にも倫理的にも大きな能力が必要とされる翻訳を軽視するような評価基準の制度化や社会的イメージは、独創的な研究や成果を促進するというよりも、むしろ知の地盤低下を招来する可能性が高いだろう。/こうした翻訳に対する過剰な軽視は、それ自体が従来の過剰な重視に対する反動である。(中略)翻訳蔑視はオリジナル重視という近代イデオロギーの反映であると同時に、また近代以前から続く神学的・形而上学的発想の残滓でもある。翻訳がなぜ貶められるのか。簡単に言えば、翻訳はオリジナルとの関係で「二番煎じ」と考えられているからである」(藤本一勇『外国語学』岩波書店、53から54ページ)
2025年7月13日日曜日
2025年7月12日土曜日
7月12日
カーラ・コルネホ・ヴィラヴィセンシオは書いている。「フロリダで保険に入っていない不法移民が経験することは、ほかの無保険の人びとのそれとさほど異なるわけじゃないけれど、それでも決定的な違いがあって、たとえ余裕があっても不法移民は保険を購入できない。この国をはじめどの西欧諸国でも右派が悪霊[ブギーマン]とみなすのは、病気の移民というイメージだ--健康保険制度への負担とされるもの、救急救命室や納税者にとってのお荷物。これを信じる人の考えを変えることにわたしがほとんど関心のないことは、何度でも言っておきたい。外国嫌いの人間[ゼノフォーブ]の考えを変えることを期待されるくらいなら、カミソリの刃を飲みこんだ方がまだまし。それでもこの病気の移民というブギーマンには興味があったから、わたしは調べてみようと思い立った」(カーラ・コルネホ・ヴィラヴィセンシオ『わたしは、不法移民 ヒスパニックのアメリカ』池田年穂訳、慶應義塾大学出版会(84-85ページ)
自ら不法移民としての経験を持ち、その後ハーヴァード大学で学んだ著者は、本書を「クリエイティブ・ノンフィクション」と呼ぶ。「綿密な取材に根ざし、詩のように翻訳され、選択された家族によって共有され、ときに読むのが苦痛な本だ。ひょっとしたら読者の皆さんは好きになれないかもしれない」(13-14ページ)
2025年7月11日金曜日
7月11日
2025年7月10日木曜日
7月10日
柴崎友香『帰れない探偵』(講談社)は「帰れない探偵」が世界をさまよう連作短篇集。収録されている最後の「歌い続けよう」のワンシーン。空港の展望デッキで、探偵はたまたま話しかけられた人と会話をする。
「(前略)わたしが通っていた高校を【子どもが】受けたいって言ってます。何年か前に移転して、すっかりきれいな校舎になってて」
「それはいいですね」
「わたしが高校のときすごく楽しかったって話をしょっちゅうしたからかも」
わたしは頷いた。
彼女からは、わたしはどう見えているだろうか?
「ライブイベントに行くん?」
わたしは聞いた。彼女は懐かしい笑顔を見せた。
「チケットが当たらへんかったから、ここから同じ空気だけでもって。でもみんな考えることはいっしょやから、ここもあと二時間で閉鎖されて特別観覧席になるみたい。びっくりするような料金で」
2人の会話が東京弁から関西弁にスイッチするところが絶妙。探偵(わたし)は、それまでは「それはいいですね」と東京弁だったが、急に「ライブイベントに行くん?」と切り替える。そして相手も「チケットが当たらへんかったから」と答える。
2025年7月9日水曜日
2025年7月7日月曜日
7月7日
メキシコの作家エレナ・ポニアトウスカは、パリに置き去りにされたロシア出身の妻アンジェリーナ・ベロフ Angelina Beloffがメキシコに帰った夫ディエゴ・リベラに宛てた1921年10月19日付の架空の手紙を書いている。「En el estudio, todo ha quedado igual, querido Diego, tus pinceles se yerguen en el vaso, muy limpios como a ti te gusta. 愛するディエゴ、アトリエは何もかも同じ、きみの絵筆はコップに立っている、きみがいつもそうするのが好きだったように、とても綺麗に洗われて」。(Elena Poniatowska, Querido Diego, te abraza Quiela, Seix Barral , p. 9)
2025年7月6日日曜日
7月6日
現実ではなく記憶を書くことについて、ジェラルド・マーティンはガルシア=マルケスの伝記で書いている。「【構想があったが筆が進まなかった『百年の孤独』が一気に書けた】ガルシア=マルケスの身にいったい何があったのか? 長い年月を経たあとになぜこの小説を書けるようになったのか? 彼はぱっとひらめき、自分の少年時代ではなく[instead of a book about childhood]、少年時代の記憶について書くべきだと気づいた[ a book about his memories of his childhood ]。現実realityではなく、現実を写実的に描いた作品[a book about the representation of reality]にしなければならない。アラカタカとそこに住む人たちではなく、彼らの世界観を通して語らなければならない。アラカタカをよみがえらせようともう一度試みる代わりに、アラカタカの人びとの世界観を通して語る(中略)必要があった」(ジェラルド・マーティン『ガブリエル・ガルシア=マルケス ある人生』木村榮一訳、岩波書店、378ページ)。
息切れについて、柴崎友香は『帰れない探偵』で書いている。「どの大陸にやってくる低気圧や豪雨をもたらす前線も年々勢力を増し、甚大な被害が起きるようなっている。先週のニュースかと思って見ていたら今日の別の災害だったりさらに別の場所の災害だったりして、記録的な災害の度に行われる寄付の呼びかけやチャリティーイベントもこのごろは息切れしている」(『帰れない探偵』177ページ)。
民主主義を適切に維持するための活動も息切れ状態だ。無茶苦茶なことを言う人が権力を握ったりすれば(そういうことは実際に起きている)、その監視にも時間を割かなければならない。一日24時間をどのように使えばよいのだろうか。ありきたりのことだけれども、力を合わせる必要がある。他の人ができないときには自分が、自分ができないときには他の人が行動し、それを細々とでも続けて息切れしないように、と思う。民主主義的な手続きで選ばれた人が民主主義を否定することはままあるが、その後、その人にはなんらかの裁きが下される。しかしそれが起きるまでには多くの時間がかかる。本当に多くの時間と人命を引き換えにしないと裁きは下されないのだ。正しく声を上げ、それを人に伝え、それが広がっていく必要がある。帰れない探偵が出身の場所に帰ることができるのはいつだろうか?
2025年7月5日土曜日
7月5日
大崎清夏は「ハバナ日記」(『目を開けてごらん、離陸するから』リトルモア)で、2018年2月1日から10日にかけて、トロント経由で行ったハバナへの旅について書いている。「ブックフェアの人混みに揉まれ、ケティの後をあっちへ行ったり、こっちへ行ったりしているうちに、スペイン語がわからないことに、というより、何もわからないまま誰かのあとをついていくしかないことに、いい加減、気持ちがばくはつしそうになってきた。さらに、実はアラマルを水曜日に引き払わなければならないことがわかり、それって今日じゃん。いつ行くの、次はどこに泊まればいいの?とケティに詰め寄ってしまった」(188から189ページ)。そして「ダニエルとカロリーナと一緒に詩の家に戻ると、扉が閉まっていて中に入れなかった。ええっ、スーツケースは?明日までスーツケースとはお別れだった。諦めて、ダニエルとタクシーに乗ってベダードに戻り、民泊の自分の部屋(があるって素敵!)でシャワーを浴びて、なんとか手持ちの服をやりくりして、グレーのタンクトップと、こういうときのために持ってきた大ぶりの三角ピアスでパーティー風に着替えた」(194から195ページ)。
2025年7月4日金曜日
7月4日
ガルシア=マルケスの語りの声は、政治制度に対しても、覇権的権力の倫理的な基盤に対しても、不遜であることで知られている。しかしその不遜さは、男性が女性に対して有する特権の神話を解体するにはいたらない。すなわち、男性性を能動的な性、攻撃性、知的探求、公的権威と並び立たせ、女性性を介護者や家事労働に矮小化するような伝統的ジェンダー階層は、彼の世界では自然化された要素である。とはいえ、逆説的なことに、彼の作品の女性たちが服従を許さない性格を持っていることも、彼のナラティブの際立った要素である。ガルシア=マルケスの女性たちは、本来的に従順ではないし、喜んで言いなりになっているわけではない。女性たちが家父長制的な期待を破ろうとする姿が描かれることで、ガルシア=マルケス世界にははからずも、カリブとラテンアメリカにおけるジェンダーと権力に内在する矛盾があらわれているのだ。(Nadia Celis-Salgado, The Power of Women in Gabriel García Márquez's world)
2025年7月3日木曜日
7月3日
柴崎友香は『帰れない探偵』(143-144ページ)で、「時間が時間の速度で過ぎた。静寂とはこういう時間のことをいうのか(後略)」「生まれて最初に聞いた言葉、話した言葉、友人たちと毎日どうでもいいようなことをしゃべり続けていた言葉は、わたしの中から消えない。長い間会っていない友人たちの声が、何十年も前に交わした言葉が、今もときどき聞こえてくる」「テラさんがあっというまに彼らの音楽に馴染んでいくのと対照的に、リズム感も運動神経もよくないので、わたしの太鼓はたどたどしかった。それでも、そのたどたどしいリズムに他の楽器の音が応答するように音楽が紡がれ、歌が響き、観客たちが声を上げた」と書いている。管啓次郎は朝日新聞(7月2日夕刊)で、ル・クレジオの『歌の祭り』を引きながら、パナマのワウナナ族の儀式について書いている。その儀式では「男も女も、子供も老人も、宙に吊るされた丸木舟のまわりに集い『祈りのように、音楽を奏でる』」「この踊りに『詩』がともなうと言うのではないが、その根拠は潜在的には言語であり、神話だ」
2025年7月2日水曜日
7月2日
2025年7月1日火曜日
7月1日
2025年6月30日月曜日
6月30日
Shu-Mei Shih(史書美)の論文「Comparison as Relation」(関係としての比較」)。誰か日本語に訳してほしい。グリッサンの『関係の詩学』を踏まえている。彼女は「The Plantation Arc(プランテーション・アーク)」を提起。これは西インド、アメリカ大陸の南、東インドを同じ構造で考えること。奴隷制のもと組織化されたプランテーション・システムの構造を出発点に、それぞれの地域で相互に関係しているが異なる一つのルートをたどること。関係としての比較。柴崎友香『帰れない探偵』からは「昔の地図が、きれいすぎる気がした。(中略)もし、書き換えられているとしたら、高い技術があり、周到に行われている」(19)、「資料は、よく整理されていた。むしろ、整理されすぎている気がした」(63)など。記録の書き換え、消去、記憶の不確かさ。もとに帰れない探偵。消えてしまった探偵の家への路地。うっすらと恐怖が立ち上がってくる。また「誰かが話すそのとき、その人が見ている光景。いつか確かに見た光景。(中略)わたしはそれが見たいのに、ずっと見ることができない」(71)から、当事者と語り手の距離感。
今日は6月30日。
2025年6月29日日曜日
6月29日
2025年6月28日土曜日
6月28日
2025年6月26日木曜日
2025年6月24日火曜日
2025年6月22日日曜日
2025年6月21日土曜日
2025年6月16日月曜日
6月16日
Rauda Jamís。日本語表記ではローダ・ジャミ。
『フリーダ・カーロ 太陽を切りとった画家』(河出書房新社、1999新装版)の著者。フランス語で書かれたフリーダの伝記。
ジャミJamísという姓。
父はファヤド・ハミス。メキシコ生まれだがキューバで長く暮らして、キューバ作家として知られている(Fayad Jamís, 1930-1988)。
母はキューバ出身で、ビブリオテカ・ブレべ賞の受賞者で詩人のニバリア・テヘラ(Nivaria Tejera, 1929-2016)。
エレナ・ポニアトウスカの本(スペイン語)をフランス語に翻訳している人でもある。
2025年6月15日日曜日
2025年6月13日金曜日
2025年6月10日火曜日
2025年6月6日金曜日
2025年6月4日水曜日
6月4日
2025年6月3日火曜日
6月3日
ビルヒリオ・ピニェーラの両親フアン・マヌエル・ピニェーラ・アベラとマリア・クリスティーナ・ジェラ・キンタナは、キューバのマタンサス州のカルデナスの教会で1909年6月23日に結婚した。この夫婦から生まれた子どもには、父方の姓ピニェーラと母方の父方の姓ジェラが使われ、〇〇〇〇・ピニェーラ・ジェラとなる。この夫婦から生まれ、のちに作家となったビルヒリオも、若いときはビルヒリオ・ピニェーラ・ジェラ名義で発表している。彼の最も早い時期の詩「El grito mudo(黙した叫び)」がそれだ。この詩はフアン・ラモン・ヒメネス篇『La poesía cubana en 1936(1936年のキューバ詩)』に見つけられる。いずれ母方の姓は消え、彼はビルヒリオ、とか、たんにピニェーラと呼ばれる。
2025年6月2日月曜日
2025年5月27日火曜日
5月27日
2025年5月26日月曜日
5月26日 近況
2025年5月25日日曜日
5月25日 近況
2025年5月18日日曜日
5月18日 近況
2025年4月14日月曜日
4月14日 『植民地文化研究』23号
ケンブリッジのシリーズで昨年出たキューバ文学史が届いた。編者はラテンアメリカ・アヴァンギャルド研究のヴィッキー・ウンルー(Vicky Unruh)と、キューバ文化・文学研究で、ソ連影響下のキューバについて業績の多いジャクリーン・ロスの二人。
The Cambridge History of Cuban Literature, Edited by Vicky Unruh and Jacqueline Loss, Cambridge University Press, 2024.
全体で785ページ。このリンクから、目次やインデックスを見ることができる。
近況として、植民地文化学会の年報『植民地文化研究』23号(2025)に、比較文学者・ポーランド文学者の西成彦さんとの往復書簡「ラテンアメリカ文学者に聞く」が掲載された。
西さんの問いかけに答える形で、これまで書いたことがないような自伝的なことも含めて、『百年の孤独』を出発点に、これまでの研究を振り返りながら、あれこれラテンアメリカ文学について論文では書いていないようなことを書いた。
移民や東アジアの文学のことまで、こういう形式だからこそ自由に書けることも多かった。ちょうどこのやりとりをしている頃に、ハン・ガンのノーベル文学賞があったりして、往復書簡でも少し触れた津島佑子の存在の大きさを思った。今後はここに書いたようなことをもとに論文その他で形にしていきたい。
2025年4月6日日曜日
2025年4月6日
4月1日、新年度がはじまった。1月から3月まで、ほぼ3ヶ月をかけて、年度を終わらせることと年度をはじめることの両方を交互にやりながら、〈晴れて〉ではなく、〈雨と雹に降られる〉寒さの中、4月ははじまった。
それでも3月の終わりには春らしい日もあって、卒業生の結婚式に招かれて鎌倉まで出かけた時は暖かい良い天気で、新郎が「晴れ男なので」と言っていたが、その通り、この3月終わりから4月にかけてあれほどの好天はあの数日しかなかったのではないかと思うくらいの晴れっぷりだった。
映画『エミリア・ペレス』を観てきたのだが、この映画は大いに問題がある。そのことを含めて評価されるべきだと思った。この映画のたいていの紹介記事には、自身トランスジェンダーであるカルラ・ソフィア・ガスコンのかつてのSNSでの発言が炎上したことが書かれているが、ここでの問題はそこではなく、この映画そのもの、この映画におけるトランスジェンダーの描き方である。
この映画の内容は、暴力の限りを尽くした麻薬王が、性別移行によって免責され、無処罰(スペイン語で言うところのimpunidad)が可能になった物語である。
ラテンアメリカにおいては暴力に対する無処罰は深刻である。『思想』2025年2月号のファノン特集で石田智恵がアルゼンチンの軍事独裁暴力の免責に触れている。
コロンビアでは麻薬カルテルの極悪犯罪人が整形手術によって身元を偽り、逮捕を逃げている。この映画では、そうした整形手術が性別移行に転用され、手術を受けた人物は処罰されることなく、その後の行動は「寛大さ」として描き替えられていく。何かがおかしいという声はどこかにあるのだろうか?
埼玉県立近代美術館の展覧会「メキシコへのまなざし」を見てきた。学期が始まる直前にゼミでフィールドワークとして募ったところ大勢参加した。
当日はこの企画を担当された学芸員の方が学生たちのために、展示の概要を説明してくださり、その後みんなで鑑賞し、質疑応答、そして再度質疑に基づいて、展示を確認できるように整えていただいた。
利根川光人はメキシコの遺跡を形にして日本に持ち帰ろうと拓本を使う。その拓本も展示され、「心臓を喰らうジャガー」などを見ることができる。質疑応答の時に学生の質問に答える形で教えていただいたのだが、拓本は石を水で濡らして和紙をあてるだけなので、墨を塗って石碑を汚したりするわけではない。しかし欧米人は見様見真似で拓本をとろうとしてインクなどを使い石碑を汚してしまったという。
いまさら気づいたのだが、今回の企画展のチラシに使われている利根川光人の「いしぶみ」という作品は、雨や雷の神チャック(Chac)がモチーフとなっている。
チャックから連想されるのはカルロス・フエンテスの「チャックモール」なのだが、チャックモールとは生贄の儀礼に用いる横たわる彫像である。フエンテスの短篇ではこの二つ、すなわち雨の神(チャック)と生贄儀礼の石像(チャックモール、この名称は作品内にもある通り、ル・プロンジョンが発見して命名した)が融合した存在として出てきているということなのだろう。
日本では、1955年に催された「メキシコ美術展」(これが東京国立博物館で催されたという点にも注目したいが)よりあと、そしてメキシコでは1950年代、双方の芸術家たちは、「現代」というものを描くに際してメキシコの神話への参照を積極的に行なったということである。展覧会図録にはこのように書かれている。
「…日本の美術家に「メキシコ美術展」の「現代美術」が提示したのは、メキシコの歴史や伝統に依拠しながらも反動的な復古主義に陥らず、かつ社会的な主題を躍動感のあるリアリズムによって表現する美術であった。それが今後の美術の在り方を模索する当時の日本に驚きと興奮をもたらしたことは想像に難くない。」(吉岡知子「メキシコへのまなざしが問いかけるもの」、展覧会図録『メキシコへのまなざし』埼玉県立近代美術館館、p.74)
2025年2月27日木曜日
2025年2月27日
昨年の秋の「キューバ危機」のあと、バイデンは任期終了直前にテロ支援国家のリストからキューバを外したが、その10日ほどあと、トランプが再指定してしまった。
昨年はハン・ガンがノーベル文学賞をとったが、ちょうどそれと前後して津島佑子の『あまりに野蛮な』を読んでいた。それにしてもハン・ガンの『別れを告げない』や津島のこの小説、こんなとてつもない小説を読むと、しばらく外に出たくなくなる。出てぶらぶら街を歩いても外の風景は全く目に入らない。頭がいっぱいになる。日常の仕事やその他あれこれをやっているべきではない時間だ。
霧社事件は1930年、済州島四・三事件は「1947年から1954年」(訳者斎藤真理子氏のあとがき参照)。
津島の本は2008年、ハン・ガンの本は2021年刊行。
どちらの小説も「魔術的リアリズム」的と言えるのだが、ナショナルヒストリーから取りこぼされる史実に向き合うときに、こういう書き方が選び出される。
それにしても、リアルタイムで津島佑子やハン・ガンが書き、それが翻訳されている。
『百年の孤独』は時間的にも距離的にも遠い話だと思って読んでいたけれど、そんなことはなくて、エドウィージ・ダンティカの『骨狩りのとき』やバルガス=リョサの『ケルト人の夢』、J.M.クッツェー(『恥辱』)、『私の名はリゴベルタ・メンチュウ』、大江健三郎(『静かな生活』)とも一緒に読めるのだ。
たとえ知っている言語の原書で読んだとしても日本語の翻訳で読んだとしても、知らない言語で書かれているかのような、新しい言葉や表現だ。
文字の連なりはわかるとしても、一語一語をたどるようにして意味をつかむ。あるいは意味はつかめなくても、一語一語をたどる。
それだけで胸がいっぱいで苦しいが、それでも読まずにはいられない。辛いのに読みたい。
その地域や「国っていうもの」や「人間」や「歴史」に近づかせ、それらについてわかったという気持ちと、絶対にわかり切ることはないという気持ちの両方を味合わせてくれる。
こういう本に帯をつけて作品やその内容を説明するのは本当に大変だろうと思う。そういう「説明」ができないところから書かれている。
津島佑子はハン・ガンを読んだのだろうか。ハン・ガンは津島佑子を読んだのだろうか。
『別れを告げない』は、『あまりに野蛮な』がなければ書かれなかったのではないか。