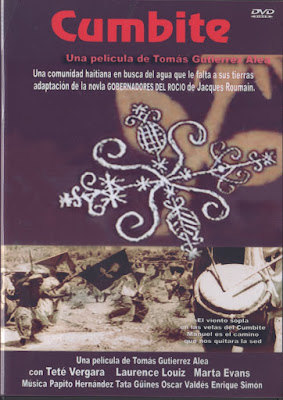キューバ映画の『クンビット』をみた。
監督はトマス・グティエレス=アレアで、1964年の映画。
15年間、キューバの砂糖黍農場で働いたハイチ人マヌエルは故郷のフォンルージュに戻った。
帰ってみると、村は土地の争いで揉め事があり、血が流れ、それ以降、人々は真っ二つに分かれている。しかも雨がまったく降らず、旱魃に苦しみ、このままでは滅亡の危機さえある。
マヌエルの父と母は息子の帰郷を喜ぶが、マヌエルは帽子を編んで街に売りにいく生活ではやっていけないと将来を案じる。水はどうしたら手に入るのか?どこかに水源があるはずだ。探索するが見つからない。
村人たちは宗教儀礼で雨乞いをするばかりだ。映画では、この儀礼の場面にたっぷり時間をとって見せてくれる。
100分程度の映画だが、雨乞い、埋葬など、儀礼の部分に相当の時間を使っている。撮り方には、なんとなくその後のアレア作品『低開発の記憶』の冒頭シーンを思わせるところがないではない。
マヌエルはそうした宗教的な慣習をあまり信じていないようにも見える。軽蔑しているわけではないようだが。映画では、そうしたマヌエルの合理的思考はキューバで培われたようにも見せている。キューバ人監督だからなのかな、と思ってしまったのだが、さて。
実はこの映画を見ようと思ったのは、この映画の原作がハイチの作家ジャック・ルーマンの『朝露の主たち』であることを知ったからである。そして教えてもらったのだが、この小説には翻訳があるという。
なんと!と思ってすぐに入手した。
ジャック・ルーマン『朝露の主たち』松井裕史訳、作品社、2020年。
ざっと読んだ限りだが、マヌエルの理知的な考えの背後にキューバがあるのは原作を踏まえているとみて良いようだ。
例えば、以下はマヌエル(映画ではスペイン語なのでマヌエルだが、原作はマニュエル)と恋人のアナイサ(同様に原作はアナイズ)との会話。
--------------
「フォンルージュまで水を引くとなると大仕事になる。みんなが力をあわせる必要があるし、和解しないとそれは無理だろう。ひとつ話をしてあげよう。キューバでは初め、何ら抗議することも抵抗することもなかった。ある人は自分を白人だと思っていて、またある人は自分を黒人だと思っていて、両者のあいだにはちょっとした不和があった。砂みたいにバラバラで、主人たちはその砂の上を歩いていた。でも自分たちがみんな似通っているとわかると、ウエルガをするために結束すると……」
「『ウエルガ』って言葉、なに?」
「君たちはむしろストライキって言うだろうね」(97-98ページ)
--------------
こんなふうにマヌエルはキューバの経験をハイチに持ち込もうとする。引用にあるように、マヌエルはスペイン語をかなり使う。15年キューバにいたからスペイン語が出てきてしまうのだ。
アナイサは敵対するグループの娘なので、彼女との将来を夢見るマヌエルだが、前途多難である。アナイサはマヌエルに会うために人目を避けつつも、実はマヌエルに引かれている。
いよいよマヌエルは泉を山で発見する。その噂は村を流れ、大騒ぎになる。「あいつはキューバから魔法の棒を持ち帰った。それで地面を叩いて水を見つけたのさ」と解釈する村人もいる。
ここで映画のタイトルの「クンビット」の話になる。「クンビット」とは、クレオール語で集団農業労働を意味する。翻訳書の解説によれば、この単語はスペイン語のconvite(招待)が語源とのこと。
善人マヌエルは、敵味方なしにみんなで水路を村に引こうと提案する。「クンビット」をしよう、と。父親は反対する。血が流れたんだぞ、協力なんてしたくない。敵方も折れてくれない。
「血は死、水は生命」との言葉を持って、話をしに行ったマヌエルなのだが、その帰り道に襲われてしまう。
が、このマヌエルの犠牲によって村は結束し……となる。